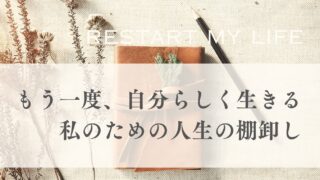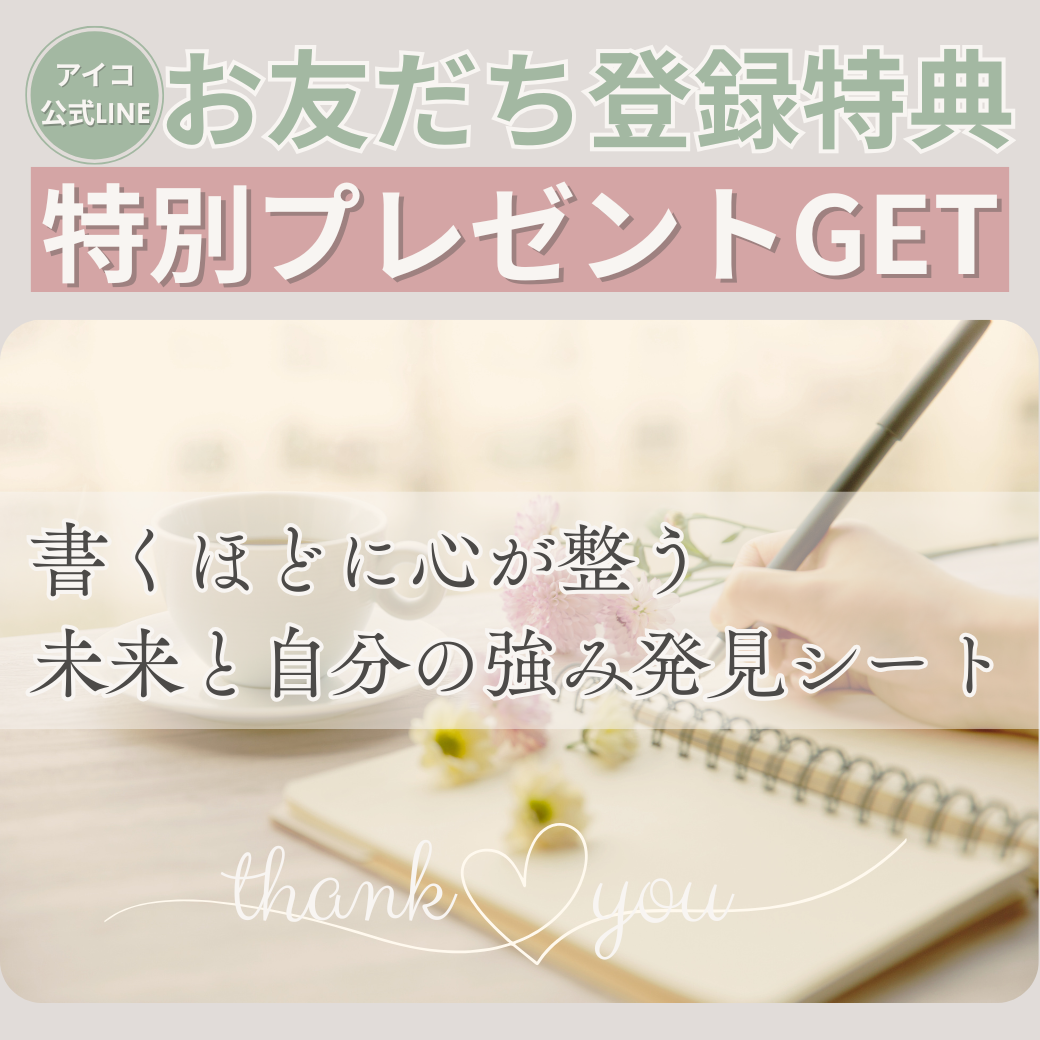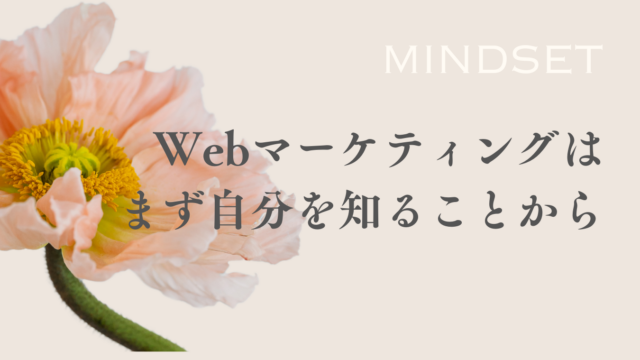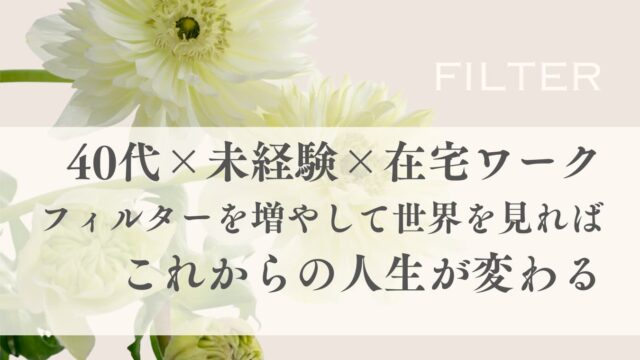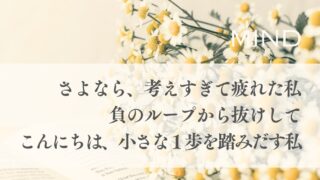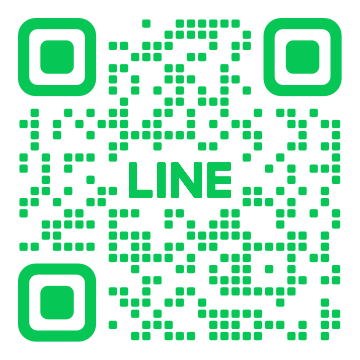このままで、終わりたくない。
子どもが手を離れて静かな自分だけの時間が増えたとき。
ふと「このままずっと夫とふたりだけの生活って、本当に私は幸せ?」
と考えたことはありませんか?
実は、私も、同じです。今、48歳の私は離婚はしていません。
でも「私らしく生きれていないのかも…」そんな想いを抱えながら暮らしています。
よぎる「離婚」という二文字…
でも、現実は、50代女性が離婚して一人暮らしを始める生活費や暮らしって?
本当に、やっていけるのかな?子どもに迷惑をかけずに自立できるのかな?
そんな不安ばかりが押し寄せてきます。
「50代からの一人暮らしの生活費って、どのくらい必要なんだろう?」
何度も検索して出てくるのは、専門家の考えや制度、数字の話ばかり。
でも、本当に知りたかったのは
「まだ離婚していない私に、今なにができるのか?」ということでした。
夫に限界を感じていても、実際には、まだ何も動けていない。
「これでいいのかな。」と感じながらも
自分の本音すら見えなくなっている人は、きっと少なくないはずです。
この記事でお伝えすること
●離婚前にこそできるお金と暮らしの備え
●今の生活を“味方”に変えるための考え方
●まだ離婚していない私が今、実際に始めていること
大切なのは誰と居たいかじゃなく、
どんな自分で生きていきたいかを選べる私になること。
未来の自分が笑顔でいられるように。
迷いながらも進もうとしている私のリアルが
あなたの明日へのヒントになったら嬉しいです。
私たちが感じる「違和感」の正体

子育ての卒業=家族の役割の終わり
子どもが独立し、時間と心に余白ができると
それまで忙しさに紛れて気づかなかった「違和感」が顔を出します。
これまで「母」として、家庭を守ることに精一杯だった。
夫との関係がどうであれ、自分のことは後回しにしてきた。
でも、今は、静まり返った家の誰もいないキッチンでつくため息が響いてしまう。
「私は“お母さん”としてここにいたんだな」
と気づいたとき、家族の中での役割が終わり
「私自身の人生」と向き合い始めるタイミングが来たということなのかもしれません。
夫婦だけの時間に広がる「沈黙」
●会話がない
●生活リズムが合わない
●気を遣ってばかり
●なんとなく家に居場所がない
同じ空間に居ても、ずっとひとりのような感覚。
こうした静かな違和感が積み重なって「このままじゃ、嫌だ」と心の蓋がふと開く瞬間があります。
「我慢」してきたこと、ありませんか?
過去に感じた小さな違和感の数々…
●距離を感じる夫との関係
●義父母との付き合い
●モラハラ
●無関心や一方通行の関係
●家事・育児を一人で担ってきた日々
「家族のために」「子どものために」
そうやって飲み込んできた言葉や感情。
でもそれが「当たり前」だったのか、自信が持てなくなる日もある。
気づけばいつのまにか50代。
子どもの自立とともに、その違和感はもう「無視できない重さ」になっていのかもしれません。
「限界」を感じているのは弱いからじゃない
それは、あなたがここまで頑張ってきた証。
だからこそ、今“もう限界かもしれない”と感じているんです。
「私が、今さら?」
「離婚なんて、何もしてこなかった自分には無理」
そう思ってしまうのは自然なことかもしれません。
たとえ目に見える成果がないように思えても
あなたが飲み込んできた言葉、背負ってきた役割、耐えてきた日々は
たしかに「今のあなた」を支えてきた大切な時間です。
だから、「まだ何もできていない私」なんて、いない。
この記事に辿り着いてくれたあなたの中には
「動こうとしている私」が、ちゃんといるんです。
離婚する・しないじゃなく、「備える」という選択肢
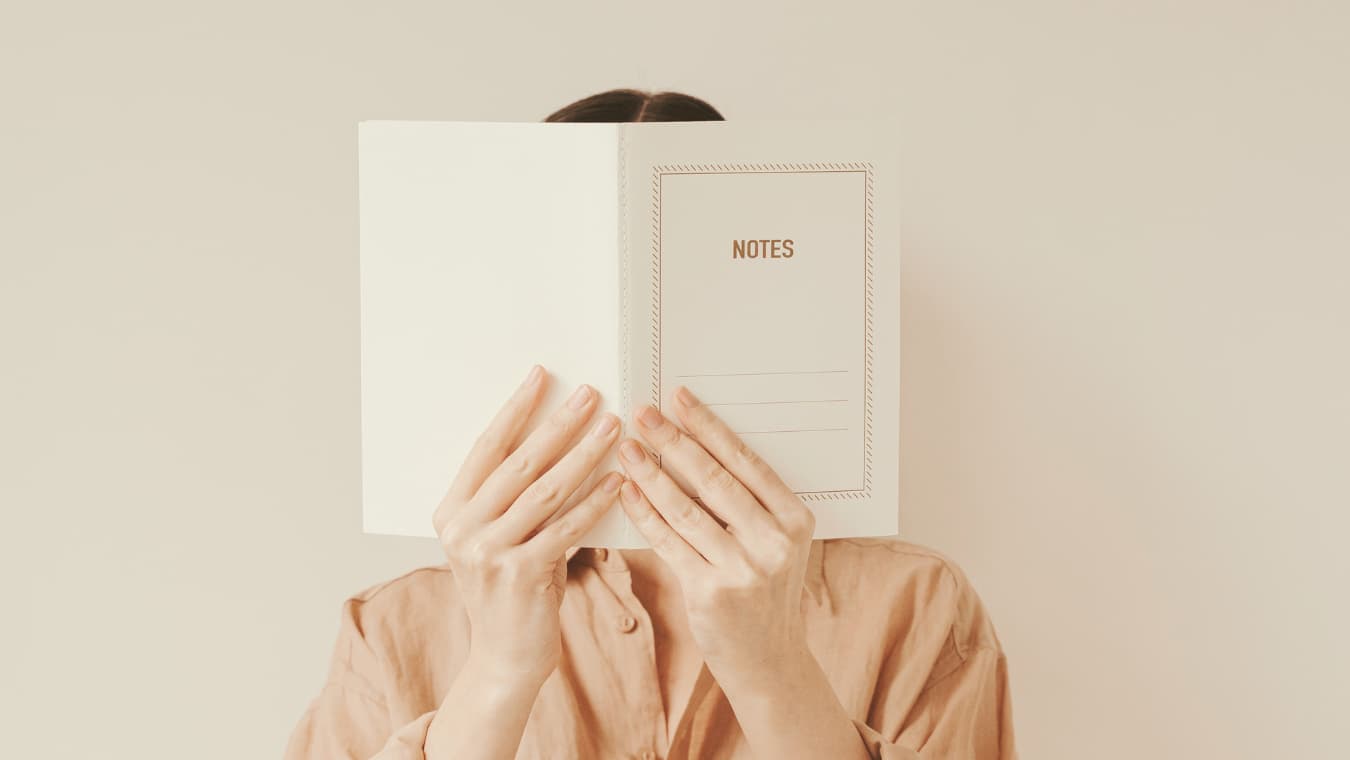 不安があって当たり前。「動けない私」はダメじゃない
不安があって当たり前。「動けない私」はダメじゃない
離婚? …そんな簡単なことじゃない。
●経済的にやっていけるか不安
●子どもには心配をかけたくない
●孤独になるのが怖い
命の危険がない日常だからこそ、「今すぐ動かなくていい理由」がいくつもある。
それでも心のどこかでは
「このままでいいのかな」と思っている自分もいる…
その声を、もう無視しなくていいんです。
まだ離婚していない今だからこそ、できること
それは、「決断」じゃなくて「準備」をしておくこと。
●生活費の目安を知っておく
→ 50代女性がひとりで暮らすには、月いくら必要か?
→ 家賃・食費・保険・老後資金などの目安を把握
●使える制度を調べておく
→ 年金分割、婚姻費用、遺族年金、ひとり親控除など
●収入源を少しでもつくっておく
→ 扶養内パート、副業、在宅ワークなど
●相談先を把握しておく
→ 弁護士の無料相談、離婚カウンセラー、年金事務所、法テラスなど
これから、どう生きたいのかを選択できるようにしておくことです。
私が今、実際にやっていること
●“今”のうちに、在宅ワークの学びをスタート
今しかできない、と思って決めました。
夫の収入で暮らせている“今”は私に与えらえたありがたい猶予期間だと捉えることに。
パートで少しずつ貯めたお金を使って、自分の未来に投資しました。
正直、もし離婚後だったら…この金額は出せなかったと思います。
●弁護士の無料相談で制度や条件を確認
「離婚弁護士 ○○(地域名)」で検索して
ホームページから“話しやすそう”と感じた方を選びました。
初回は無料。内容によっては追加料金を払えば継続して話を聞いてもらえます。
相談の前には
・これまでの経緯を時系列でまとめたメモ
・世帯収入や家族構成
・必要なら、夫の言動の記録や証拠(日記など)
を用意しておくと、話がスムーズに進みます。
相手は弁護士さん、プロです。そして何のしがらみもない!
知らなかったことを“知っておく”だけでも、気持ちがラクになりました。
●生活費のシミュレーション
今の生活から、必要最低限の支出を洗い出しました。
まだわからない部分は、ざっくりとでも概算。
・家賃にいくらかかる?
・食費、光熱費、通信費は?
・どこなら削れる?何は絶対必要?
“完璧な見積もり”じゃなくていいんです。
今の自分の生活にいくら必要かを知ることで、「やっていけるかも」が生まれます。
●住みたい街の賃貸情報を見る
これはまだ現実的に動くためではなく、ちょっと息抜きのような感じです。
街の相場も知ることができ「この街で暮らすなら、月○万円か…」
と考えたりすることで少しだけ“自由な未来”を想像できるんです。
●自分に合いそうな働き方を調べて試してみる
メンタルや体力、これまで培ってきたスキルやキャリアは人それぞれ。
ひとりになったとき、自分の体力や心の状態で
どんな働き方なら続けられるか?
それを知らずに一歩を踏み出すのは、やっぱり怖かったので
私は「できること」ではなく「できそうなこと」も考えました。
今の自分の体力、精神的余力、家にいる時間。
それに合わせた収入の目標を立てて、いま、そこに向かって少しずつ動いています。
▶なぜそれが在宅ワークだったのかについてはこちらでくわしくお話しています。
●子どもたちに話すということ
そしてもう一つ、大切にしていることがあります。
それは、大人になった子どもたちに、「母」としてではなく
「ひとりの人間としての私のこれから」を話すようにしています。
それを知ってもらうことが、私にとって大きな支えになっています。
もちろん、当てにして、頼るためではありません。
ただ、一番、身近な大切な存在に、自分の想いを
まず“わかってもらえる”こと安心は心を軽くしてくれます。
50代女性の一人暮らし、生活費と収入

ひと月にかかる生活費はいくら?
総務省『家計調査年報(2023年)』によると
50代単身女性の平均的な月間支出はおよそ16〜17万円。
たとえば、仮に東京都で一人暮らしをした場合の月支出は…
家賃:7万円(地域・物件により変動)
食費:3万円
光熱費・通信費:1.5万円
医療費・日用品:1万円
国民健康保険・年金:2.5〜3万円
雑費・交際費:1.5万円
合計:約16〜17万円
これはあくまで「生活できる最低ライン」
今後の物価上昇やライフスタイルによって、もっと必要になる場合もあります。
最低、必要な「額面収入」
手取り17万円を得るには、額面22万〜23万円程度の月収が必要です。
所得税・住民税:約2.5万円
国保・年金:約3万円
「え…そんなに必要なの?」と感じた方もいるかもしれません。
私も最初は、正直ゾッとしました。
でも、「知らない」ことで感じる不安が、実は、一番大きいんですよね。
現実的な働き方を考えてみる
現実的な働き方って、何があるの?
たとえば…
●スーパーのレジ=14万円程度
時給1200円×6時間×週5日
●副業でWebライターなど=3万円程度
→ 合計:月17万円程度
いきなり仕事を変えたり、専業主婦の場合は新しくパートを始めるのは
怖いかもしれないけれど
「少しだけ収入をつくってみる」「支出を見える化してみる」
その積み重ねが、“私はきっとやっていける”という安心につながります。
いざというとき慌てないように、今のうちにできること
●少しずつ収入源をつくる
●支出を見える化する
●自分に合った働き方を見つける
離婚を決断する前にこそ
「自分で生活を立てられる力がある」と感じられること。
それは、未来の自分への最高の備えだと私は思っています。
離婚したらどうなる?|お金のことと公的機関

いざというとき、慌てず、焦らず、自分を守るためには
「知っておくこと」が一番の味方になります。
そして何より、私たちはこれまで、本当にたくさんのことを我慢してきました。だからこそ、公的に認められた制度や支援は、“当然に受け取っていい権利”なんです。
年金分割制度|離婚後2年以内が期限
厚生年金や共済年金に加入していた配偶者との離婚時に、その年金を分割してもらう制度。
3号分割:2008年以降の厚生年金は、相手の同意なしで分割可能
合意分割:2008年以前の期間は、話し合いや調停が必要
離婚から2年以内に手続きをしないと無効になってしまうので
備えておきたい制度のひとつです。
財産分与|専業主婦でも対象
婚姻期間中に築いた財産を公平に分け合う制度。
たとえ名義が夫であっても共有財産として2分の1ずつ請求できる権利があります。
対象は、現金・預金・不動産・退職金・保険・車・家電・家具など
もちろん、専業主婦でも請求できます。
離婚前でも、共有財産の確認と整理は進めておいて損はありません。
・通帳や保険、契約書類などの情報をリストアップ
・必要なら証拠の保全(コピー・写真)をしておくとスムーズ
婚姻費用|別居中の生活費は“請求しなければもらえない”
実は、離婚前の“別居中”でも生活費を請求する権利があります。
これは「婚姻費用」といって、夫婦である限り成り立つ法的な支援です。
金額は、配偶者の年収、夫の年収や子どもの有無によって金額が算定されます。
請求日以降しか認められないため、請求は早い者勝ちのようです。
▶婚姻費用の自動計算ツール【新算定表対応|最新2025年版】はこちらから
無料で相談できる公的機関を活用
いきなり弁護士に行くのはハードルが高い…
そんな方は、以下の無料の窓口から始めてみてください。
年金事務所:年金分割の試算や手続き相談・シミュレーションが可能
法テラス:離婚に関する無料法律相談(所得制限あり)
ハローワーク:職業訓練や女性向け支援窓口
「聞くだけでもOK」なんです。
まずは“知っておく”こと。それが、未来の安心に変わっていきます。
離婚したらどうなる?|住まいと公的支援

「離婚して一人になったら、どこに住むんだろう…」
実は、年齢を重ねるほど「住まい」はハードルが高くなる現実があります。
特に60歳を過ぎると、賃貸の審査に通りにくくなるというケースも。
理由は主に3つ・・・
●収入が不安定になりやすい
●孤独死のリスクを大家さんが懸念
●保証人がいない/頼みにくい
でも、大丈夫。
これらのリスクをあらかじめ知って備えることで、選択肢を広げていくことができます。
公的保証制度の利用
初期費用(敷金・礼金)に備えた貯蓄
自治体の住宅扶助・住居確保給付金などをチェックしておく
初期費用と地域の家賃補助制度
賃貸契約には家賃の4〜5ヶ月分の初期費用がかかることも。
敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などで家賃の4〜5ヶ月分必要
自治体によっては、住宅扶助や住居確保給付金が利用できる
知らないうちに「想像以上にお金がかかる…」と焦らないためにも
相場感と支援制度の把握は早めにしておきたいところです。
選択肢を広げるヒント
公営住宅:家賃が安く、ひとり親や低所得者に優遇あり
実家に戻る:経済的メリットは大きいが介護問題も
リースバック:持ち家を売却しながら住み続けられる制度
今は選ばないとしても、「こんな道もあるんだな」と知っておくだけで
いざというときの気持ちが軽くなります。
支援制度一覧
生活保護:収入・資産が一定以下の人への支援・最低限の生活を保障(資産・収入要件あり)
住居確保給付金:失業や減収時の家賃相当額の補助(最大9ヶ月)
寡婦控除・ひとり親控除:所得控除により税負担が軽減
ハローワークの職業訓練制度:資格取得支援、給付金あり再就職のための支援制度も多数
条件が合えば、以下の制度が生活の支えになります。
住まいの不安は、日々の安心に直結しますよね。
でも、知っているだけで救われる制度がたくさんあるんです。
「そのとき考えればいいや」ではなく、
「今のうちに選択肢を持っておくこと」それが、未来の自分を守る準備になります。
離婚した場合/離婚しない場合の違い
それぞれの選択肢にどんな現実があるのかを知って
そのうえで「私は、どうしたいのか?」を考えることが大事です。
経済面の違い
| 離婚した場合 | 離婚しなかった場合 | |
|---|---|---|
| 財産分与 | 原則2分の1請求可。 退職金や保険も対象。 |
分与なし。夫の死後、相続が発生。 |
| 年金分割 | 離婚後2年以内に手続きで分割可。 | 不可。 遺族年金の受給要件に該当すれば可能。 |
| 住まい | 財産分与で持ち家を出る可能性。 賃貸の審査に不安も。 |
現住居に住み続けられる可能性が高い。 名義・維持費確認は必須。 |
| 生活費 | すべてを自力で稼ぐ必要あり。 | 夫の収入や年金と共有。 補助的に働く選択も可能。 |
心と体の違い
| 離婚した場合 | 離婚しなかった場合 | |
|---|---|---|
| 心の自由 | ストレスや無関心からの解放。 「眠れるようになった」という声も。 |
関係次第では違和感が継続し、心の孤立感も。 |
| 孤独感 | 自由と引き換えに不安が増す場面も。 | 一緒にいるけれど“孤独な同居”の可能性も。 |
| 自立の実感 | 「私の人生を生きている」と感じられること増える。 | 「このままでいいのかな?」という思いが残り続けることも。 |
老後・家族・社会的立場の違い
| 離婚した場合 | 離婚しなかった場合 | |
|---|---|---|
| 老後資金 | 年金・副収入・貯蓄で備える必要あり。 | 夫の年金・遺族年金・相続などで設計可能。 |
| 終活・介護 | すべて自力で設計。 地域サービスが頼り。 |
配偶者・子どもの支援が視野に。 関係性に左右される。 |
| 社会的信用 | 再就職・賃貸などで不利になることも。 | 配偶者ありの安定イメージで手続きがスムーズ。 |
どんな未来を選びたいのか
●どの不安なら受け入れられる?
●どの自由を私は大切にしたい?
●どんな「私」で生きていたい?
その答えは、他の誰でもない、自分の中にあります。
だからこそ、この章で見てきた「違い」は、
「どっちを選べば損しない?」というための比較ではなく
「どんな未来を、自分の意志で選びたいか」
を見つけていくためのヒントにつながるはずです。
「まだ離婚していない今」だからこそできること
 離婚はまだ切り出していない。切り出されたわけでもない。
離婚はまだ切り出していない。切り出されたわけでもない。
だからこそ私は、夫の収入で生活できている“今”のこの時間を
「ありがたい猶予期間」として使おうと決めました。
離婚の決断はすぐにしなくてもいい。
でも備える力は、今からでも育てられます。
「あのとき、準備しておいてよかった」と思えるように。
この道を選んでよかったと思える未来を、自分にプレゼントしてあげましょう。
我慢してきた私が、自分を選ぶ側になる
これまで、たくさん我慢してきたと思います。
子どものために。
家族のために。
波風を立てないために。
もちろん、楽しいこともあった。
この道を選んできたのは、自分自身。
でもふと思ったんです。
「私は、いったい何のために我慢してきたんだろう?」
もしそれが“子どものため”だったのなら
その子どもたちは、母親が人生を楽しんでいないことを本当に望むでしょうか?
私たちが子どもたちの幸せを願ってきたように
彼らもまた、自分の人生を楽しんでいる“私”を見たいのではないか。
そして、その子どもたちはもう独立し、自分の足で歩いています。
だから、あなたも、これからは「我慢しない私」をえらんでもいい。
もう選んでいいんですよ。
その力をつけたとき、どうしたい?
もし、あなたが
いつでもひとりで生きていける「力」を持てたとしたら
どんな未来を選びたいと思いますか?
●夫と暮らしながら収入と生活を共有しつつ、自由に趣味や仕事を楽しむ?
●それとも「私はやっぱり違う人生を生きたい」と、一歩踏み出す?
どちらを選んでも、間違いではありません。
大切なのは、「選べる私」でいること。
「誰といるか」より「どんな私でいたいか」
 離婚するか、しないか。それはゴールではないと思います。
離婚するか、しないか。それはゴールではないと思います。
結婚がそうであったように「これからの生き方」を選ぶためのひとつの岐路。
だからこそ、
自分の意志で“選べる力”を持っておくことが、これからの私たちを守ってくれます。
離婚を経験した女性たちの声
「離婚届けを出して役所を出た瞬間、空ってこんなに青いんだと思った」
「もう夫の足音を気にせず、ゆっくり眠れるようになった」
「自分のお金を自分のために気兼ねなく使えるようになった」
「好きなものに囲まれて暮らす生活は静かで自由」
「腐ることもたまにあるけど、せっかく生まれて来たんだから楽しまなきゃ!」
想像するだけで、心が軽くなるような言葉たち。
あなたもそうありたいと思いませんか?
自分で選び「私を生きていく」
離婚をする、しない。
このテーマは、人生の中でもとても大きな選択です。
そして、本当に大切なのは
「どんな私で生きていきたいか」を、自分の意思で選べるようになること。
これまで私たちは、“私より誰か”を優先する場面が多かったかもしれません。
でも、これからは義務ではなく、我慢でもなく、誰かの期待でもなく
「自分で選んだ人生」を、生きていい。
今、心のどこかで「このままでは嫌だ」と感じているなら、
それは、自分らしい人生を生きたいというサイン。
離婚をしなくてもいい。
でも、“準備しておく”ことはできます。
誰といるか、ではなく
「どんな私で在りたいか」を自分で選ぶ。
自分の人生を「選べる私」へ。
これまでがんばってきたあなた自身の人生をリスタートする一歩が踏み出せますように。
画面を通して出会えたことに心から感謝しています
ぜひ、私ももがき悩みながら「私の人生」を歩けるようにがんばります。一緒にがんばりましょうね。